こんにちは!
打楽器初心者指導シリーズ、第3回目の今回は、「初心者がつまずくポイントとその対策」について詳しく解説していきます!
誰でも最初は、失敗したり、なかなか上手くいかなかったりするのは当たり前です。
しかし、指導する側が「どんなところでつまずきやすいか」を事前に知っておけば、効果的なサポートができます!
この記事では、打楽器初心者がよく陥りがちな「壁」とその原因、そして具体的な解決策や指導のコツを紹介します!
この記事を読めば、初心者の「できない…」に慌てず対応でき、スムーズな成長を後押しできるようになるはずです!
ぜひ、日々の指導に生かしてみてください!
参考にしている教則本はこちら!
初心者がつまずくポイントと対策:先回り指導でスムーズな成長を!
- 「あれ?なんだか上手くいかないな」
- 「ここでいつも引っかかるな」
初心者の指導をしていると、このような場面に遭遇することがあります。
これらの「つまずきポイント」を事前に把握し、その原因と対策を知っておくことは、指導をスムーズに進め、初心者のモチベーション低下を防ぐ上で非常に重要です。
ここでは、打楽器初心者が特につまずきやすいポイントをいくつか挙げ、それぞれの原因と具体的な対策、指導のヒントについて詳しく見ていきましょう!
- 楽器の持ち方・構え方:間違った癖は早期発見・修正
- スティックコントロール:力の入れすぎ、脱力できない
- リズム感:拍に乗れない、リズムキープが難しい
- 楽譜の読み方:音符、記号が理解できない
- 音色の変化:同じ叩き方しかできない、強弱がつけられない
- 各楽器特有のつまずきポイント
順番に紹介します!
楽器の持ち方・構え方:間違った癖は早期発見・修正
まず最初に、そして非常に重要なのが、楽器の持ち方や演奏時の姿勢(構え方)です!
これが正しくできていないと、どんなに練習しても良い音が出なかったり、変な癖がついて後々苦労します。
最悪の場合、体を痛めてしまう原因にもなりかねません。
- 猫背になってしまう。
- 楽器に近づきすぎたり、逆に離れすぎたりする。
- 肩や腕に変な力が入ってしまう。
- 楽器の高さが合っていない。(特に立って演奏する場合)
初心者がやりがちな間違いとしては、このようなものが挙げられます。
これは、緊張していたり、楽譜を見るのに必死だった、単純に正しいフォームを知らない、ということが原因として考えられます。
どの打楽器を演奏する場合でも、正しいフォームの基本は次の4つです。
- 背筋を自然に伸ばす。
- 肩の力を抜き、リラックスする。
- 楽器に対して適切な距離と角度で立つ(または座る)。
- 楽器の高さや角度を、自分の体に合わせて調整する。
指導のポイントとしては、まず最初に正しいフォームを丁寧に教え、その後も定期的にチェックすることが大切です。
練習の始めに必ずフォームを確認する習慣をつけると良いでしょう。
写真や動画を撮って客観的に見せてあげるのも、自分の癖に気づくきっかけになりますよ。
癖がついてしまう前に、根気強く、繰り返し指導していきましょう。
スティックコントロール:力の入れすぎ、脱力できない
打楽器演奏の基本中の基本であり、多くの初心者が最初にぶつかる壁が、スティックやマレットのコントロール、特に「脱力」です。
力を抜いてリラックスした状態でスティックを操ることは、綺麗な音色、速いフレーズ、豊かな表現力、そして長時間の演奏に不可欠です。
しかし、初心者は「しっかり叩かなきゃ!」という意識から、次のような状態に陥りがちです。
- スティックを強く握りしめてしまう。
- 手首がガチガチに固まってしまう。
- 肩や腕の力だけで叩こうとしてしまう。
また、逆に力が抜けすぎて、スティックを落としそうになったり、音が弱々しくなったりすることもあります。
力が入ってしまう原因は、やはり緊張や、「良い音を出そう」「速く叩こう」という焦り、あるいは単純に脱力した状態での演奏感覚を知らない、といったことが考えられます。
脱力のコツは、次の3点です!
- グリップ(持ち方)を確認する
→必要以上に強く握らず、親指と人差し指(または中指)で支点を作り、他の指は添える程度にする。
- 手首のスナップを意識する
→腕全体で叩くのではなく、手首を柔らかく使ってしなやかに振る感覚を掴む。
- スティックのリバウンド(跳ね返り)を利用する
→打面からの自然な跳ね返りを殺さずに、次の音に繋げる意識を持つ。
練習方法としては、まず練習パッドなどを使って、非常にゆっくりとしたテンポで一音一音、フォームや力の入り具合を確認しながら叩く練習が効果的です。
脱力した状態でスティックが自然に跳ね返る感覚を掴む練習や、指先を使って細かいコントロールをする練習なども取り入れると良いでしょう。
指導者は、言葉で「力を抜いて!」と言うだけでなく、具体的なイメージが湧くような言葉で伝えたりすることが大切です!
脱力の感覚を掴むには時間がかかることも多いので、焦らず根気強く付き合ってあげてください!
リズム感:拍に乗れない、リズムキープが難しい
打楽器奏者にとって、正確なリズム感は命とも言える重要な要素です。
アンサンブル全体のリズムを支え、安定させる役割を担っているからです。
しかし、初心者の段階では、
- テンポが一定に保てない(だんだん速くなったり、遅くなったりする)。
- リズムが正確でない(音符の長さが甘い、いわゆる「ハシリ」や「モタリ」)。
- 拍の裏(裏拍、アップビート)を感じるのが苦手。
といった課題が見られることがよくあります。
原因としては、まだ音楽経験が浅く、体の中にしっかりとしたテンポ感や拍子感が身についていないことや、自分の演奏に集中するあまり、周りの音やメトロノームを聴く余裕がないことなどが考えられます。
リズム感を養う方法はいくつかありますが、以下の3つは取り組みやすいです。
- メトロノームを常に使う習慣をつける
→個人練習はもちろん、パート練習でも積極的に活用しましょう。
- リズムを声に出して歌う
→楽譜を見ながら「タン・タ・ウン・タタ」のように声に出してリズムを読むことで、頭と体でリズムを理解しやすくなります。
- 体でリズムを取る
→足で拍を踏んだり、手拍子をしたり、体を軽く揺らしたりしながら演奏することで、リズムに乗りやすくなります。
練習方法としては、まずは四分音符や八分音符などの基本的なリズムパターンを、様々なテンポでメトロノームに合わせて正確に叩く練習から始めましょう。
慣れてきたら、クリック音を抜く練習(例:4拍子の2拍目と4拍目だけクリックを鳴らす)なども、リズムキープ能力の向上に効果的です。
こちらの記事で紹介している基礎練習が、最初は特におすすめです!
指導者は、初心者がメトロノームに合わせて叩けていない時に、一緒に手拍子をしたり、隣で簡単なリズムを叩いてあげたりして、正しいテンポやリズムを体感させてあげると良いでしょう!
リズム感は一朝一夕に身につくものではないので、焦らず、楽しみながらトレーニングを続けることが大切です!
楽譜の読み方:音符、記号が理解できない
打楽器の楽譜は、リズムを中心に書かれていることが多く、メロディー楽器の楽譜とは少し見た目が違うため、戸惑う初心者もいます。
楽譜が正確に読めないと、曲の練習がスムーズに進まなかったり、間違ったリズムで覚えてしまったりする原因になります。
初心者が特につまずきやすいのは、次の点です。
- 音符や休符の種類と長さが覚えられない(特に付点音符や連符など)。
- 拍子記号の意味がよく分からず、拍の取り方が不安定になる。
- タイやスラー、アクセントなどの記号の意味や演奏方法が分からない。
- 繰り返し記号(リピート、ダル・セーニョ、コーダなど)を見落としてしまう。
原因は、単純に知識不足である場合が多いです!
複雑なリズムを図形として捉えるのが苦手だったり、楽譜を読むこと自体に苦手意識を持ってしまっていたりすることもあります。
楽譜の読み方を分かりやすく教えるコツは、
- 図解や表を使う
→音符や休符の種類と長さの関係を図で示したり、記号の一覧表を作ったりして、視覚的に理解する。
- 最初は非常に簡単な楽譜から始める
→四分音符と四分休符だけで書かれたような、ごく簡単なリズム譜からスタートし、少しずつ新しい要素を加えていく。
- 声に出して歌う(リズム・ソルフェージュ)
→声に出してリズムを読む練習を繰り返し行う。
指導のポイントは、一度にたくさんの情報を詰め込まず、一つずつ確実に理解できているか確認しながら進めることです。
繰り返し練習することが重要なので、パート練習の最初に少しだけ楽譜を読む時間を取り入れるのも良いでしょう。
楽譜に自分で書き込みをすること(カウントを書く、難しいリズムに印をつけるなど)を推奨するのも、理解を深める助けになります!
音色の変化:同じ叩き方しかできない、強弱がつけられない
打楽器の大きな魅力の一つは、その多彩な音色です。
しかし、初心者のうちは、どうしても同じような音しか出せなかったり、楽譜に書かれた強弱(ダイナミクス)を上手く表現できなかったりすることがあります。
これでは、せっかくの打楽器の表現力が活かせません。
つまずきの原因としては、次のようなことが考えられます。
- いつも楽器の同じ場所を同じように叩いてしまっている。
- 力の入れ具合(スピードや重さ)をコントロールできていない。
- 曲や場面に合ったスティックやマレットを選べていない(または持っていない)。
- 音色の変化や強弱の付け方に対する意識が低い。
音色を豊かに変化させるためには、様々な音色の違いを知ることが大切です!
- 叩く場所を変えてみる
→太鼓の真ん中、少し端、リム(縁)に近い場所など、叩く位置によって音がどう変わるか試してみる。鍵盤楽器なら、音板の真ん中か端かでも響きが違います。
- 叩く強さやスピードをコントロールする
→弱い音(ピアノ)から強い音(フォルテ)まで、段階的に音量を変化させる練習をする。スティックを振り下ろすスピードや、打面に当てる瞬間の力の入れ具合を意識します。
- スティックやマレットの種類、角度を変えてみる
→硬いマレットと柔らかいマレット、太いスティックと細いスティック、当てる角度などによって、音の硬さや響きが変わります。
強弱(ダイナミクス)を豊かに表現するためには、単に力を入れ具合だけでなく、体全体の使い方(体重移動や呼吸など)を意識したり、その音楽が持つイメージ(優しい感じ、力強い感じなど)を想像したりすることも大切です。
指導者は、まず自分がお手本として様々な音色や強弱を聴かせることが重要です。
そして、「もっと硬い音で」「もっと響かせるように」「ここはそっと触れる感じで」など、具体的な言葉で求める音色のイメージを伝えましょう。
初心者が色々な叩き方を試行錯誤することを奨励し、良い音が出た時には、すかさず褒めてあげることで音色への探求心が育ちます。
各楽器特有のつまずきポイント
これまで挙げてきたポイントは多くの打楽器に共通するものですが、楽器によっては、さらに特有の難しさやつまずきポイントが存在します。
ここでは、代表的な楽器をいくつか例に挙げてみましょう。
スネアドラム
- 綺麗なロール(トレモロ)ができない(左右の粒が揃わない、音が途切れる)。
- リムショット(リムと打面を同時に叩く奏法)が安定しない、または痛い。
- ゴーストノート(ごく小さな音で装飾的に入れる音)のコントロールが難しい。
対策:左右均等に叩く練習、リバウンドコントロール、脱力、様々なダイナミクスでの練習。
参考記事




バスドラム(コンサートバスドラム)
- 一定のテンポで叩き続けられない、リズムが不安定になる。
- ロール(特に小さい音量でのロール)の音量や粒立ちが安定しない。
- 小さい音(ピアノ)を綺麗に、かつ響きを伴って出すのが難しい。
- マレットの持ち方が安定しない、または腕や肩に余計な力が入ってしまう。
- 音を止める(ミュートする)タイミングや方法が適切でない。
対策:メトロノーム練習、手首や腕の柔軟な使い方、正しい構え方と打点の意識、脱力、適切なマレットの選択、ロールやミュートの集中練習。
参考記事



シンバル(合わせシンバル、サスペンデッドシンバルなど)
- 合わせシンバルを鳴らした後、音がすぐに止まってしまう(響きがない)。
- 合わせシンバルを合わせるタイミングがずれる。
- サスペンデッドシンバルを綺麗にロールできない、または音の止め方が汚い。
対策:合わせる角度や位置の研究、脱力、周りの音をよく聴く、マレットの選択、ミュート(音を止める)技術の練習。
参考記事



ティンパニ
- 音程が正確に合わせられない(チューニング)。※ペダル操作と耳での確認が必要。
- マレットの選択が適切でない(求める音色に合っていない)。
- ロールが綺麗に繋がらない、音量が安定しない。
対策:音感を鍛える練習、チューニングメーターの活用、様々なマレットでの試奏、手首を使った均等なストローク練習。
参考記事




鍵盤打楽器(マリンバ、シロフォンなど)
- 正しい音板を叩けない(ミスタッチが多い)。
- マレットの選択が適切でない。
- 音階やアルペジオ(分散和音)がスムーズに演奏できない。
- 4本マレット奏法(両手に2本ずつ持つ奏法)が難しい。
対策:正確な打点の練習、楽譜の先読み、スケール練習、ゆっくりなテンポからの練習。
参考記事


小物楽器(トライアングル、タンバリンなど)
- 意外と綺麗な音を出すのが難しい(叩く場所、持ち方、力加減)。
- 細かいリズムやロールが難しい。
- 楽器の持ち替えがスムーズにいかない。
対策:楽器ごとの奏法の研究、専用の練習、持ち替えの練習。
参考記事




指導者は、担当する楽器特有の難しさも理解し、適切なアドバイスや練習方法を提示してあげる必要があります。
もし自分の専門外の楽器であれば、その楽器の教則本を読んだり、経験豊富な奏者にアドバイスを求めたりすることも大切です。
すぐに解決できる方法は少ないので、一つ一つの楽器と丁寧に向き合っていきましょう。
まとめ
今回は、打楽器初心者がつまずきやすいポイントと、その対策について詳しく紹介しました!
- 持ち方・構え方:癖がつく前に、正しいフォームを根気強く指導する。
- スティックコントロール:脱力の感覚を掴ませ、リバウンドを利用する練習を促す。
- リズム感:メトロノーム活用、歌う、体で感じる、といった多角的なアプローチで養う。
- 楽譜の読み方:視覚的な工夫や反復練習で、少しずつ着実に理解を深める。
- 音色の変化:様々な叩き方を試させ、音色への意識と表現力を育む。
- 楽器特有のポイント:各楽器の難しさを理解し、適切なアドバイスを行う。
初心者がつまずくのは当たり前のことです。
大切なのは、指導者がそのポイントを予測し、原因を理解し、適切な対策を講じてあげることです。
そして何より、失敗しても責めずに、「大丈夫だよ」「一緒に頑張ろう」と温かくサポートし続ける姿勢が重要です。
つまずきは、成長のための大切なステップです。
それを乗り越えた時、初心者は大きな達成感と自信を得ることができます。
日頃の指導に、ぜひこの記事で紹介した視点や対策を取り入れてみてください!
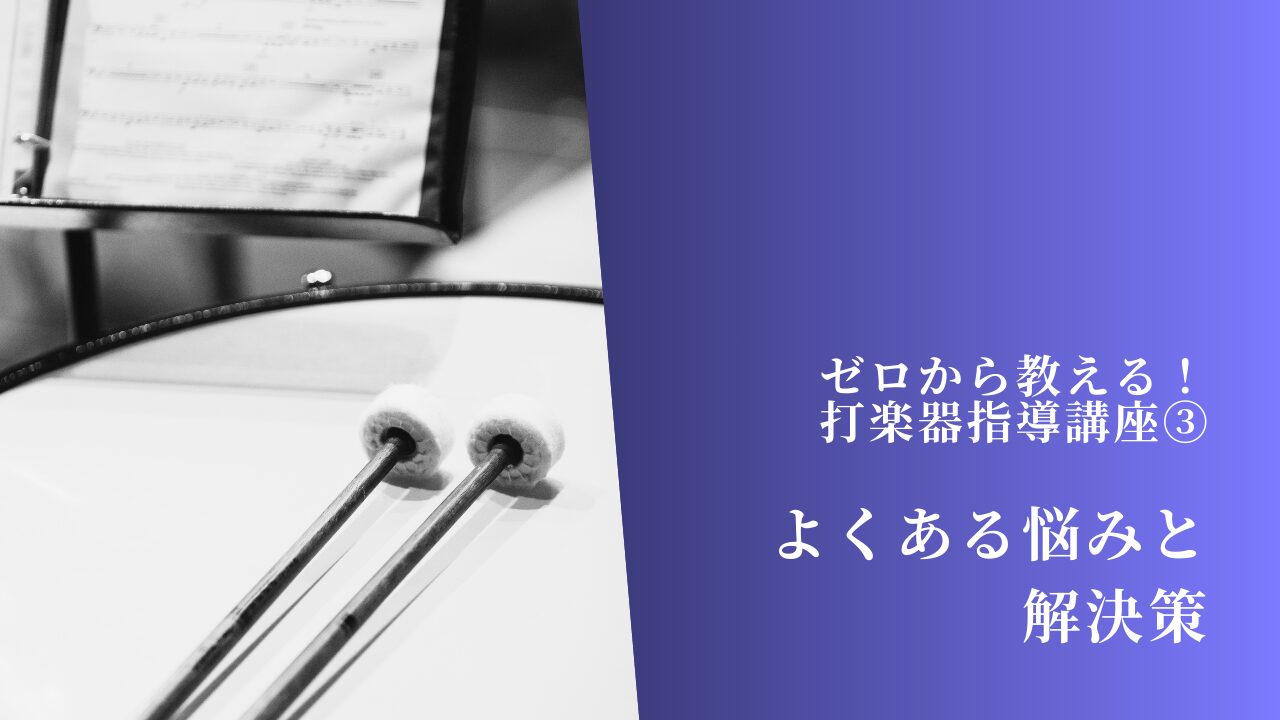








コメント