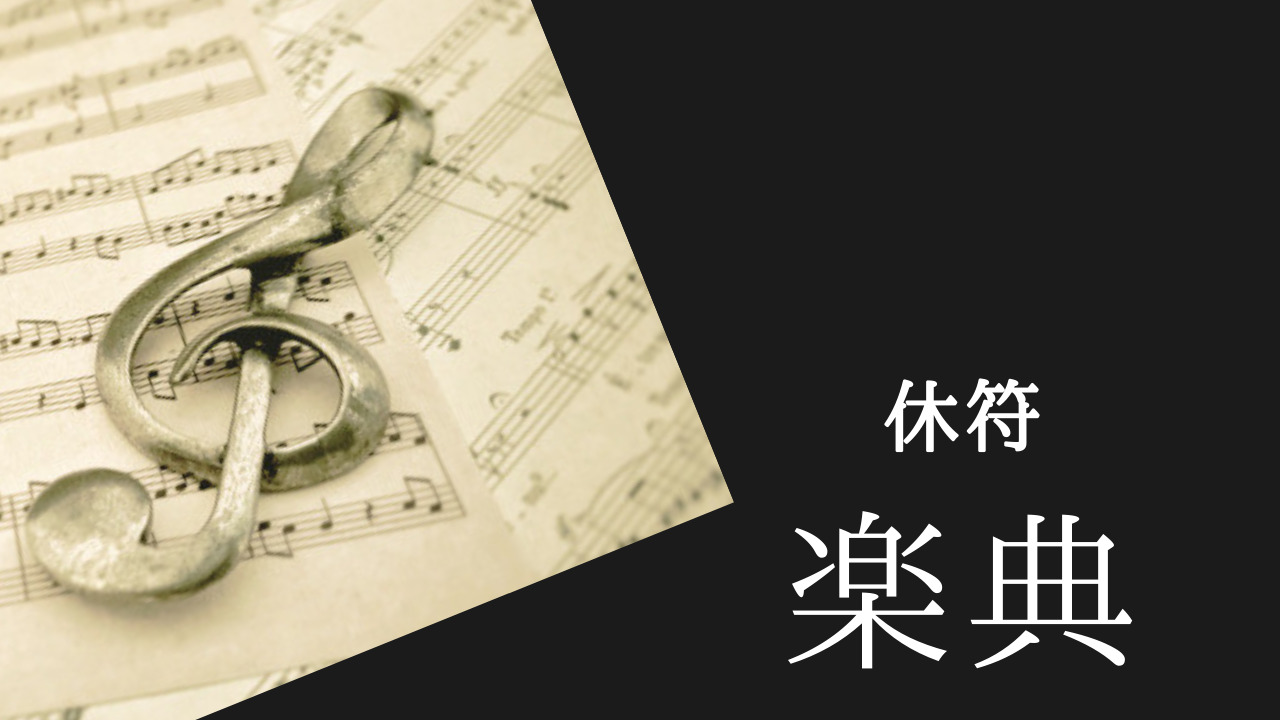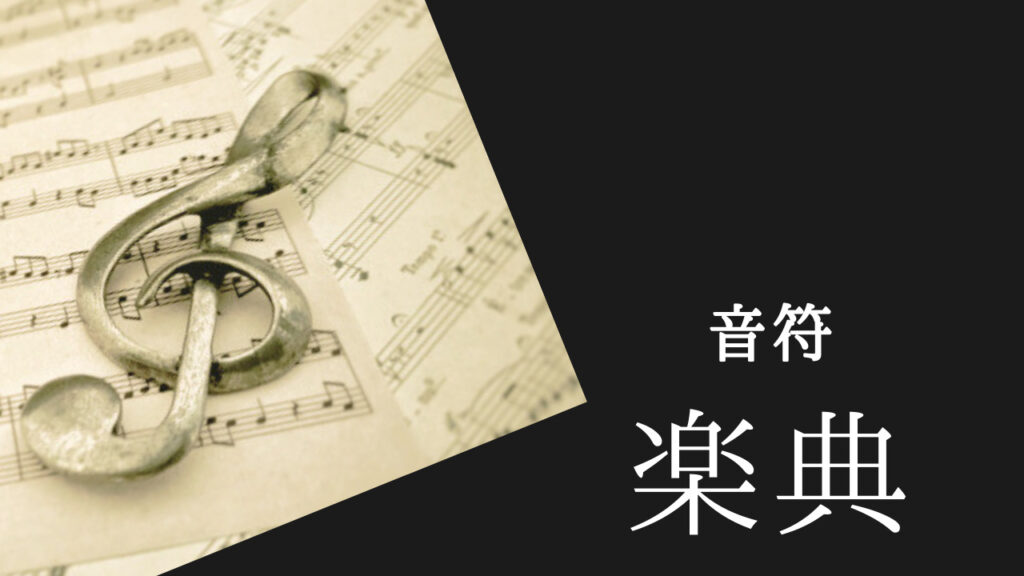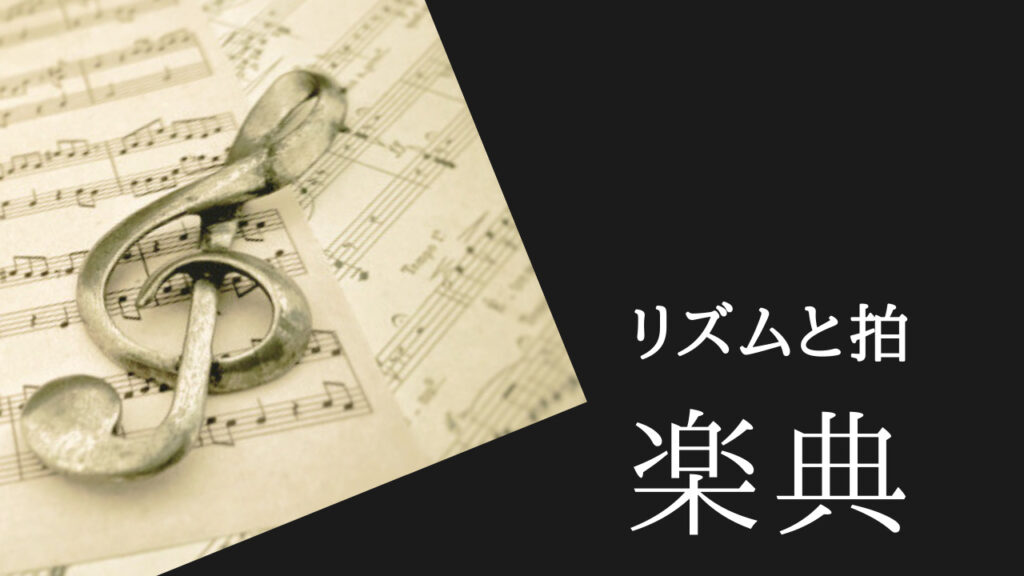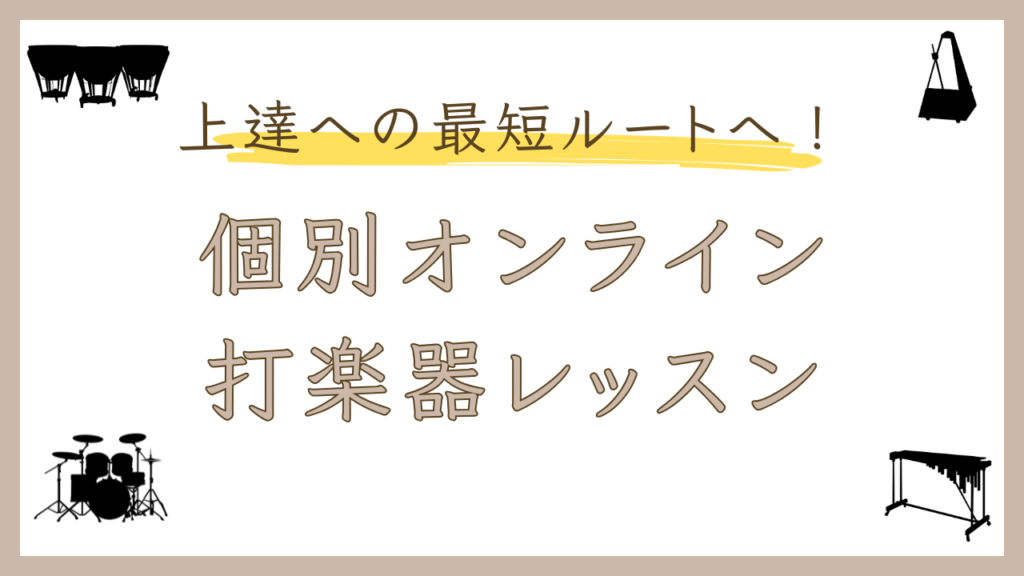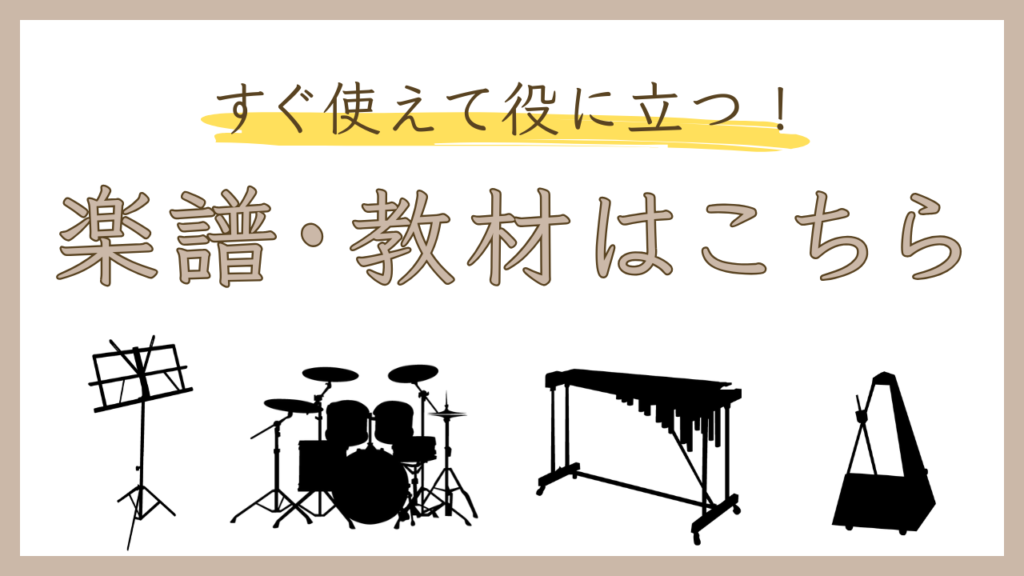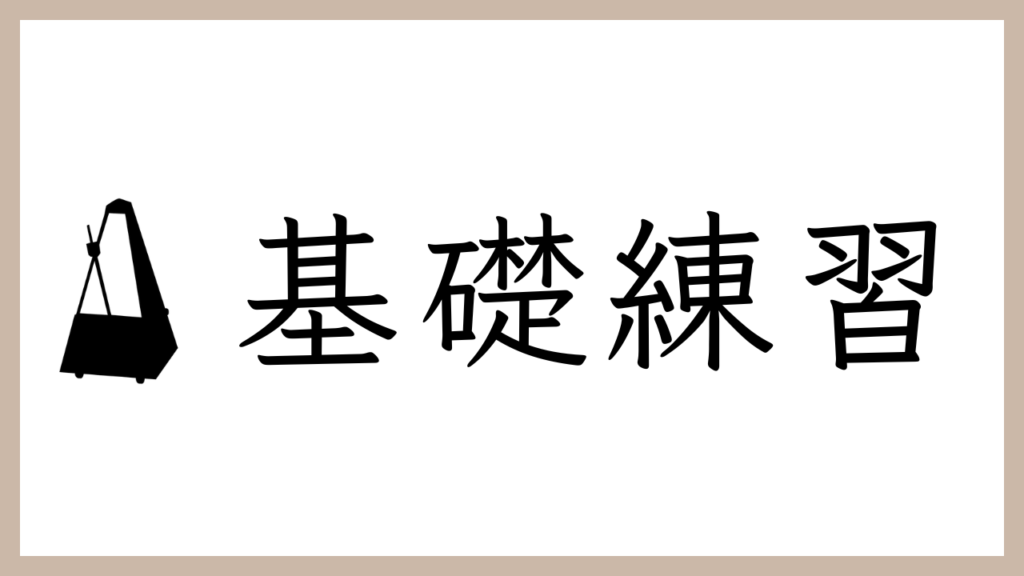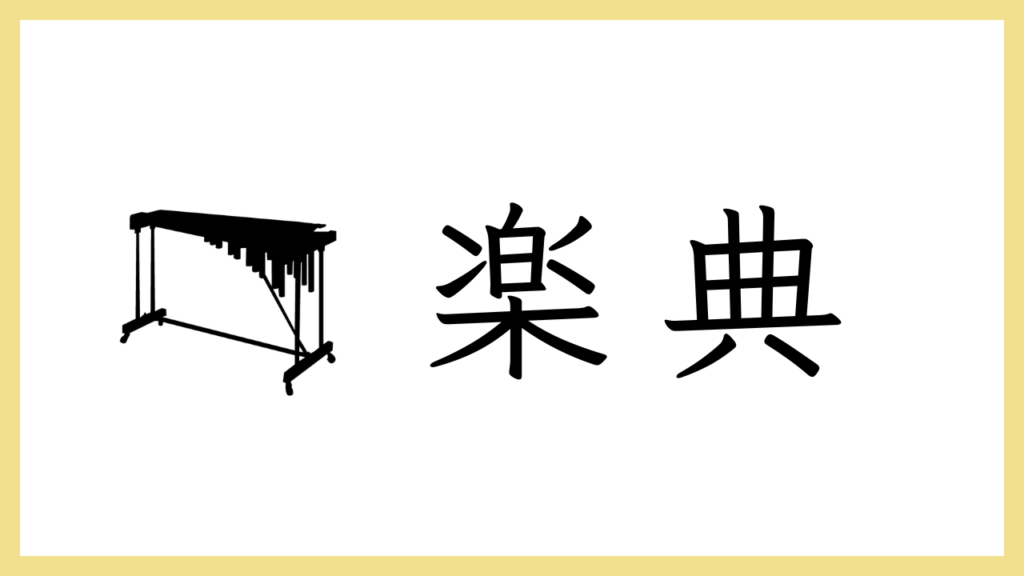こんにちは!
「休符」とは、音を出さない時間を表す記号です!
是非、最後までご覧ください!
参考にしている書籍はこちら!
「休符」について
今回紹介する一般的な「休符」です!
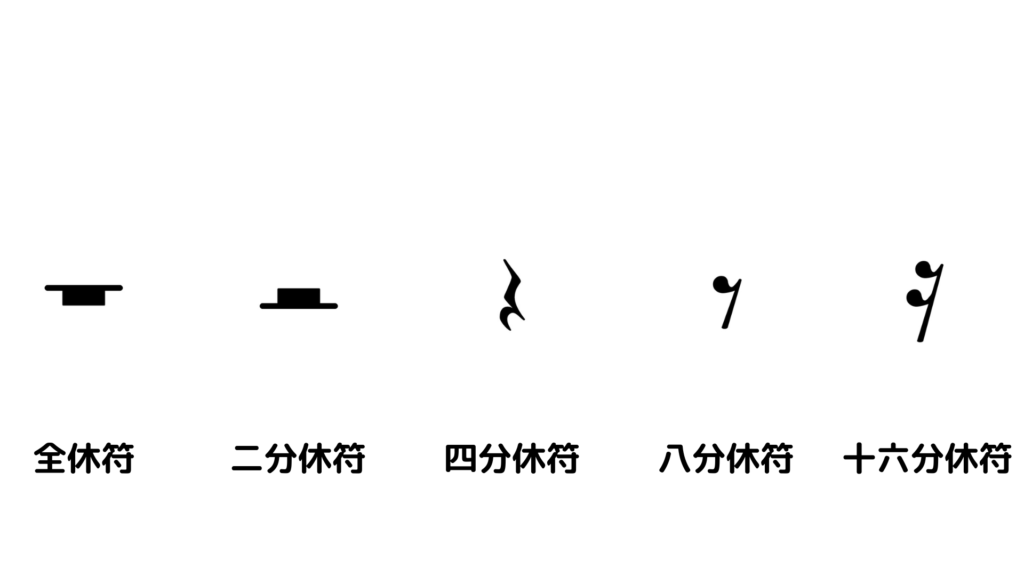
「休符」の変化・・・全休符から二分休符
「音符」と同様に、「休符」の見た目と音を出さない時間の関係をまとめていきます!
「休符」には音符の「たま」「ぼう」「はた」のように、各部分の名称や決まった形はありません!
まずは、「全休符」から「二分休符」を紹介します!
「全休符」→「二分休符」
- 「休符」の見た目・・・・・・線の下の■部分が線の上に移動する。
- 音を出さない時間の長さ・・・半分になる。
「全休符」と「二分休符」の見た目は似ています。
覚え方は、それぞれ覚えやすい方法で良いのですが、私はこう覚えました!
- 全休符の状態で、上の線に■がくっついていたが、下の線の上に落ちた。
- 上から2つ目の線と線の間を、上から順に半分ずつ埋めた。
他に、覚え方があったら教えてください!
「休符」の変化・・・二分休符から四分休符
次に「二分休符」から「四分休符」です!
「二分休符」→「四分休符」
- 「休符」の見た目・・・・・・全く異なる。
- 音を出さない時間の長さ・・・半分になる。(全休符の1/4になる。)
「四分休符」はこれまでと違い、形状もかなり独立していますね。
「四分休符」をよく見たら、ひらがなの「そ」を斜めに書いたらそれっぽいですね!
ポイントは、下から書き始めることです!
初めて書く人は慣れないと思うので、ゆっくり書いてみると良いでしょう!
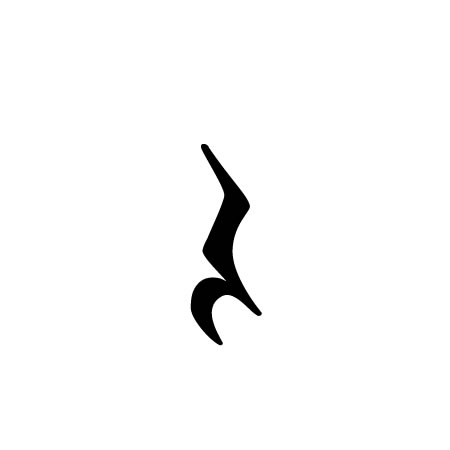
- ひらがなの「つ」の左右反転バージョンを斜めに書く。
- 左上に向かって直線を引く。
- 右上に向かって直線を引く。
- 左上に向かって直線を引く。
「休符」の変化・・・四分休符から十六分休符
「四分休符」から「八分休符」です!
「四分休符」→「八分休符」
- 「休符」の見た目・・・・・・全く異なる。
- 音を出さない時間の長さ・・・半分になる。(全休符の1/8になる。)
「八分休符」は、ひらがなの「て」と書き順が同じです!
「て」の直線部分を曲げて、曲線部分をまっすぐにすれば「八分休符」ですね!
最後に、「八分休符」から「十六分休符」です!
「八分休符」→「十六分休符」
- 「休符」の見た目・・・・・・ひげ状の部分が1つ増える。
- 音を出さない時間の長さ・・・半分になる。(全休符の1/16になる。)
「十六分音符」への変化は、音符とほとんど同じですね!
音符と合わせて理解すると良いでしょう!
「音符」「休符」の長さ
では、実際の「音符」と「休符」の長さを数字で見ていきましょう!
音楽では、音の長さを「拍」という単位で表現することが多いです!
今回は、真ん中の「4分音符」を1拍として表現します!
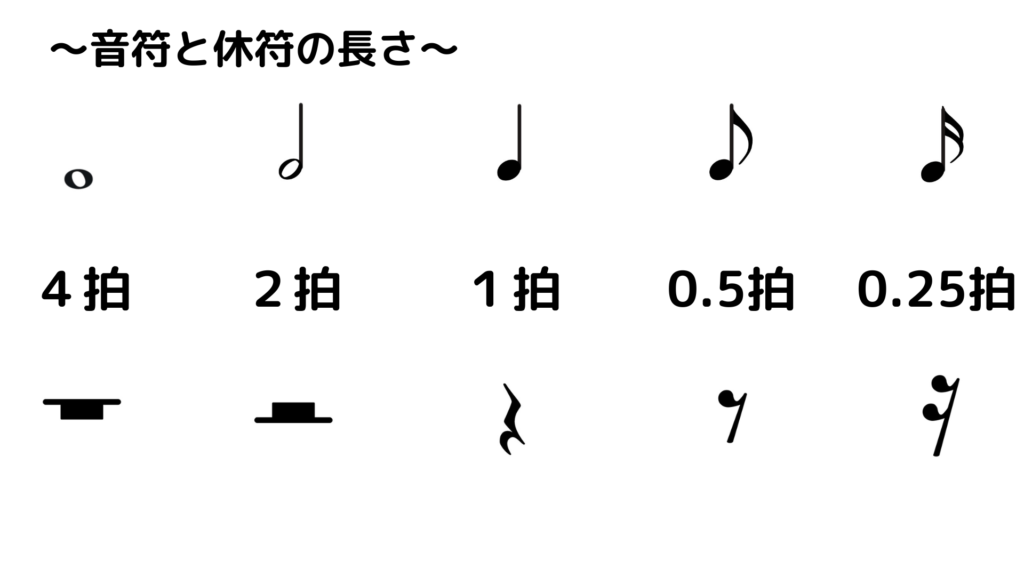
ポイントは、次の2つです!
- 名前が同じ音符と休符(図を縦に見たときに並んでいるもの)は、対応する拍の数が同じ。
- 音の長さなどは、右に行くにつれて短くなる。(半分ずつに変化していく)
これらの「音符」や「休符」が表す「拍」の長さが、今後楽譜を見ていく上で重要になってきます!
何度も見たり、調べたりして、覚えていきましょう!
まとめ
今回の記事では、以下の内容を紹介しました!
- 「休符」の見た目や意味について
- 「音符」や「休符」が表す時間の長さ