こんにちは!
今回は、指導者自身のスキルアップに焦点を当て、「もっと伝わる!教え上手になるためのコツ!」について解説していきます!
これまで、初心者のモチベーション維持や基礎練習の方法などについてお伝えしてきましたが、どんなに良い知識を持っていても、それを効果的に「伝える」力がなければ、指導はうまくいきません。
この記事では、初心者に分かりやすく、そして楽しく技術を伝えるためのコミュニケーション術や、指導者として持っておきたい視点、具体的なテクニックなどを幅広く紹介します!
この記事を読めば、あなたの指導がもっとスムーズになり、初心者の成長をより力強くサポートできるようになるはずです!
ぜひ、ご自身の指導を振り返りながら、日々の指導に生かしてみてください!
参考にしている教則本はこちら!
もっと伝わる!教え上手になるためのコツ!
打楽器の演奏技術を教えるだけでなく、初心者の心に響き、やる気を引き出すような指導をするためには、指導者自身のスキルアップも欠かせません。
筆者自身も全てを完璧にこなせているわけではありませんが、ここでは、より効果的に指導を進めるための考え方や、具体的な実践テクニックについて紹介していきます!
- 良い指導者に必要な資質とは?
- 信頼関係を築くコミュニケーション
- 「見る」技術:観察力を磨く
- 百聞は一見に如かず:効果的なデモンストレーション
- 伝わる言葉を選ぶ力
- 理解度を確認する質問力
- 効果的な練習計画の立て方
- 個人指導とパート練習の使い分け
- 指導者自身の成長:振り返りのススメ
順番に紹介します!
良い指導者に必要な資質とは?
まず、「良い指導者」とはどんな人でしょうか?
もちろん高い演奏技術を持っていることは大切ですが、それだけではありません。
初心者を導き、成長をサポートするためには、以下のような資質も非常に重要になってきます。
- 情熱:打楽器や音楽に対する愛情、そして「教えたい」「育てたい」という熱意。この情熱は、必ず初心者に伝わります。
- 共感力:初心者の立場に立ち、彼らが何を感じ、何に困っているのかを理解しようとする姿勢。
- 忍耐力:初心者の成長には時間がかかります。すぐにできなくても焦らず、根気強く、丁寧にサポートし続ける力。
- 柔軟性:一人ひとりの個性や理解度に合わせて、指導方法を調整できる力。マニュアル通りにいかないことも多いです。
- 向上心:常に新しい知識や指導法を学び続け、自分自身の指導スキルを高めようとする意欲。
人間的な魅力や温かさも、初心者が安心して指導を受け、信頼関係を築く上で大切な要素です。
完璧な指導者を目指す必要はありませんが、これらを意識することで、より良い指導に繋がっていくはずです!
信頼関係を築くコミュニケーション
効果的な指導を行う上で、初心者との間にしっかりとした信頼関係を築くことは、何よりもまず重要です。
「この人の言うことなら聞いてみよう」「この人になら質問しやすいな」と思ってもらえなければ、どんなに的確なアドバイスもなかなか届きません。
信頼関係を築くためのコミュニケーションのポイントとして、私は次のようなことを意識しています!
- 挨拶と声かけを大切にする
→練習の始めと終わりに、明るく笑顔で挨拶をします。「今日の調子はどう?」「何か分からないことない?」など、気軽に声をかけます。
- 相手の話をよく聞く
→指導者が一方的に話すだけでなく、初心者の話に耳を傾け、興味を示したり、相槌を打ち、共感します。
- 適度な雑談
→音楽以外の共通の話題(学校生活、好きなことなど)で雑談を交わすことで、心理的な距離が縮まり、親しみやすさが生まれます。
- 相談しやすい雰囲気を作る
→「いつでも質問してね」「分からないことは恥ずかしいことじゃないからね」と伝え、初心者が安心して疑問や悩みを打ち明けられるような、オープンな雰囲気を作るよう心掛けています。
指導者と初心者の間に信頼関係があれば、初心者は安心して練習に集中でき、アドバイスも素直に受け入れやすくなります。
日々の小さなコミュニケーションの積み重ねが、強固な信頼関係の土台となるのです。
「見る」技術:観察力を磨く
「教える」ためには、まず相手の状態を正確に「見る」ことが必要です。
初心者の演奏をただ漫然と眺めるのではなく、注意深く観察し、課題点や改善点、そして良い点を見抜く「観察力」を磨きましょう。
観察すべきポイント
- 演奏フォーム
→姿勢、楽器の構え方、スティックやマレットの持ち方、力の入り具合(力みすぎていないか、逆に抜けすぎていないか)など。
- 音
→音色、音量、リズムの正確さ、粒立ちの均一さなど。
- 楽譜との照らし合わせ
→楽譜通りに演奏できているか、記号などを理解しているか。
- 表情や態度
→楽しそうか、集中しているか、困っている様子はないか、疲れていないかなど。初心者の心理状態を読み取るヒントになります。
- 周りとの関わり(パート練習時)
→他のメンバーの音を聴いているか、コミュニケーションは取れているか。
観察すべきポイントは、単に技術的な側面だけではありません。
優れた指導者は、これらの点を総合的に観察し、初心者が今どんな状況にあり、何に困っていて、どんなサポートが必要なのかを的確に判断しています。
例えば、リズムが不安定な場合、単にリズム感が悪いだけでなく、フォームが悪くて叩きにくいのかもしれない、あるいは緊張して力が入っているのかもしれない、といった多角的な視点を持つことが大切です。
観察力を磨くには、経験も必要ですが、常に「なぜそうなっているのだろう?」と疑問を持ち、注意深く見続ける意識を持つことが第一歩です。
百聞は一見に如かず:効果的なデモンストレーション
言葉で説明することも大切ですが、特に動きや音に関わる指導では、実際にやって見せる「デモンストレーション」が非常に効果的です。
「こうやって叩くんだよ」「こういう音を目指そう」と、指導者がお手本を示すことで、初心者は具体的なイメージを掴みやすくなります。
効果的なデモンストレーションのポイント
- ゆっくり見せる
→速い動きは、初心者は目で追うことができません。特にフォームやスティックの軌道などを見せる場合は、極端なくらいゆっくりとした動きで、ポイントを強調しながら見せましょう。
- 良い例と悪い例を見せる
→正しいフォームや良い音だけでなく、「こういうやり方は良くないよ」という悪い例も見せることで、その違いがより明確になり、理解が深まります。
- 様々な角度から見せる
→正面からだけでなく、横からや後ろからなど、角度を変えて見せることで、より立体的に動きを捉えることができます。
- 言葉での説明と組み合わせる
→「今、手首をこう使ったの、分かったかな?」「このくらい力を抜くと、こんなに響くんだよ」のように、見せながらポイントを言葉で補足すると、さらに分かりやすくなります。
デモンストレーションは、指導者の演奏技術を披露する場ではなく、あくまで、初心者の理解を助けるための手段です。
初心者の目線に立ち、「どう見せれば一番分かりやすいか」を常に考えて、効果的なデモンストレーションを心がけましょう。
伝わる言葉を選ぶ力
指導において、「何を言うか」はもちろん、「どう言うか」も非常に重要です。
せっかく的確なアドバイスをしても、言葉の選び方一つで、初心者の受け取り方は大きく変わってしまいます。
伝わる言葉を選ぶためのポイント
- 専門用語を避ける
→初心者は、打楽器に関する専門用語(ルーディメンツ、フラム、パラディドルなど)を知りません。できるだけ日常的な、分かりやすい言葉で説明しましょう。もし専門用語を使う場合は、必ずその意味を丁寧に解説します。
- 具体的、かつ簡潔に
→抽象的な表現(例:「もっと音楽的に」)は避け、「ここのクレッシェンドをもっと滑らかに始めてみよう」「この8分音符をもう少し短く切ってみて」のように、具体的に何をすれば良いのかが分かるように伝えます。また、長々とした説明も避け、要点を絞って簡潔に話すことを心がけます。
- 理由も添える
→「なぜ」そうするのか、その理由や目的も一緒に伝えることで、初心者は納得感を持ち、より深く理解することができます。
(例:「ここで力を抜くと、スティックが自然に跳ね返って次の音が楽に出せるようになるよ」)
- 比喩表現を活用する
→感覚的なことを伝える際に、具体的なイメージが湧くような比喩を使うのも効果的です。
(例:「手首を鞭のようにしならせて」「熱い鉄板に触るみたいに、叩いたらすぐ手を離す感じ」)
- ポジティブな言葉を選ぶ
→できるだけ肯定的で前向きな言葉を選びましょう。注意する際も、まず良い点を認めてから伝えるなどの工夫をします。
言葉は、指導者と初心者をつなぐ大切なツールです。
相手の理解度や反応を見ながら、常に「どう言えば一番伝わるか」を考え、言葉を選ぶ意識を持ちましょう。
理解度を確認する質問力
指導は、指導者から初心者への一方通行であってはいけません。
初心者が本当に内容を理解しているのか、疑問や不安を抱えていないかを確認するために、「質問」を活用することが大切です。
効果的な質問のポイント
- 「はい/いいえ」で終わらない質問をする
→「分かった?」と聞くだけでは、分かっていなくても「はい」と答えてしまうことがあります。「今の説明で、どこが一番分かりにくかった?」「〇〇について、自分の言葉で説明してみてくれる?」のように、相手が具体的に答えなければならないようなオープンな質問を心がけましょう。
- 考えるきっかけを与える質問
→「どうしてここは上手くいかないんだと思う?」「他にどんな叩き方ができそう?」のように、答えを教えるだけでなく、初心者に考えさせるような質問を投げかけることで、主体的な学びを促します。
- 安心できる雰囲気で質問する
→初心者が「こんなこと聞いてもいいのかな…」とためらわないように、「どんな小さなことでも聞いてね」という姿勢を示し、質問しやすい雰囲気を作ることが前提です。
- 質問のタイミング
→説明の途中や、練習の区切りなど、適切なタイミングで質問を挟み、理解度を確認しながら進めましょう。
質問は、初心者の理解度を測るだけでなく、コミュニケーションを深め、自分で考える力を育むための重要なツールです。
効果的な質問力を身につけることで、指導の質は格段に向上しますよ。
効果的な練習計画の立て方
限られた時間の中で初心者を効果的に上達させるためには、しっかりとした練習計画を立てることが重要です。
行き当たりばったりの練習では、なかなか成果は上がりません。
効果的な練習計画を立てるポイント
- 目標設定
→まず、短期的(今日、今週)および中長期的(1ヶ月後、発表会まで)な目標を具体的に設定します。目標が明確になることで、練習内容も決まってきます。
- 段階的な難易度設定
→初心者の現在のレベルに合わせて、無理なくステップアップできるような難易度の練習メニューを組みます。基礎から応用へと、少しずつ難易度を上げていくことが大切です。
- 基礎練習と曲練習のバランス
→基礎練習は重要ですが、そればかりではなく、実際に曲を演奏する練習のバランスを考えましょう。基礎練習で学んだことを曲の中でどう活かすかを意識させると、練習の目的意識が高まります。
- 練習メニューの具体化
→単に「基礎練習」とするのではなく、「シングルストローク(テンポ80-120)を5分間」「教則本の練習曲〇番を練習する」のように、具体的な内容と時間を決めると、集中して取り組みやすくなります。
指導者は、初心者と相談しながら、個々のレベルや目標に合った練習計画を作成し、定期的に見直していくことが望ましいです。
計画的に練習を進めることで、効率的に技術を習得し、着実な成長を実感できるようになりますよ。
個人指導とパート練習の使い分け
指導の場面には、マンツーマンで行う「個人指導」と、パートメンバー全員で行う「パート練習」があります。
それぞれの特性を理解し、目的に合わせて効果的に使い分けることが、指導の質を高める上でとても大切です!
個人指導のメリット
- 一人ひとりのレベルや課題に合わせた、きめ細やかな指導が可能。
- 苦手な部分を集中的に練習できる。
- 細かいフォームや音色のニュアンスなどを丁寧に伝えられる。
- 初心者も質問しやすい。
個人指導のポイント
- 個々の目標を設定し、弱点克服や表現力の向上に焦点を当てる。初心者とのコミュニケーションを密にする。
パート練習のメリット
- パート全体のレベルアップ、アンサンブル能力の向上が図れる。
- 他のメンバーの音を聴き、合わせる練習ができる。
- 一体感や連帯感が生まれ、モチベーション向上に繋がることもある。
- 教え合いが生まれ、コミュニケーションが活性化する。
パート練習のポイント
- パート全体の目標を設定し、リズム感や音量のバランスを統一する練習、合奏練習を中心に行う。全員が参加できるような工夫(レベル別の課題など)も必要。
個人指導とパート練習は、どちらか一方だけが良いというわけではありません。
個人指導で発見した課題をパート練習で意識させたり、パート練習で必要になった技術を個人指導で集中的に練習したりと、両者を連携させることで、より効果的な指導が可能になります。
それぞれの練習時間の目的を明確にし、バランス良く取り入れていきましょう。
指導者自身の成長:振り返りのススメ
指導スキルは、一度身につけたら終わりではありません。
指導者自身も、常に学び続け、成長していくことが大切だと考えています。
そのために有効なのが、「振り返り」の習慣です。
振り返りのポイント
- 指導記録をつける
→今日の指導で何を教えたか、初心者はどんな反応だったか、上手くいったこと、課題だと感じたことなどを簡単にメモしておきましょう。客観的な記録は、後で振り返る際に非常に役立ちます。
- 自己評価する
→「今日の指導は分かりやすかっただろうか?」「もっと良い伝え方はなかっただろうか?」など、自分の指導を客観的に評価してみましょう。上手くいった点も、改善点も、どちらも大切です。
- 初心者からのフィードバックを求める
→勇気がいるかもしれませんが、「今日の練習、どうだった?」「分かりにくいところはなかった?」など、率直な意見を聞いてみるのも、大きな学びになります。
- 他の指導者から学ぶ
→今他の先輩や先生がどのように指導しているのかを見学させてもらったり、指導に関する本を読んだり、研修会に参加したりするのも、視野を広げる良い機会です。
- 試行錯誤を楽しむ
→最初から完璧な指導ができる人はいません。色々な方法を試し、「これは上手くいった」「これはあまり効果がなかった」という経験を積み重ねていくことが、指導者としての成長に繋がります。
指導は、教える相手である初心者だけでなく、教える側の指導者自身をも成長させてくれる素晴らしい機会です。
日々の指導を丁寧に振り返り、改善点を見つけ、試行錯誤を繰り返すことで、あなたの指導スキルは着実に向上していくはずです。
まとめ
今回は、打楽器初心者の指導において、指導者自身のスキルを高め、「もっと伝わる!教え上手になるためのコツ!」について、以下のポイントから解説しました。
- 良い指導者の資質:技術だけでなく、情熱や共感力、忍耐力なども大切。
- 信頼関係:挨拶や傾聴、相談しやすい雰囲気作りで、安心できる関係を築く。
- 観察力:演奏だけでなく、表情や態度からも課題や心理状態を読み取る。
- デモンストレーション:ゆっくり、具体的に、良い例・悪い例を示して理解を助ける。
- 言葉選び:分かりやすく、具体的に、理由も添えて、ポジティブな言葉で伝える。
- 質問力:一方通行を防ぎ、理解度を確認し、考える力を育む。
- 練習計画:目標を設定し、段階的に、バランス良く、飽きさせない工夫を。
- 個人指導とパート練習:それぞれの特性を理解し、目的に合わせて使い分ける。
- 振り返り:記録、自己評価、他者から学ぶ姿勢で、指導者自身も成長する。
教え上手になるための道に、終わりはないと考えています!
しかし、今回紹介したような視点やテクニックを意識し、日々の指導で実践していくことで、あなたの指導は必ず、より分かりやすく、より効果的になっていくはずです!
そして何より、あなた自身が指導を楽しむことが、初心者にとっても一番の学びになるかもしれません。
日頃の指導に、ぜひこれらのコツを取り入れてみてください!
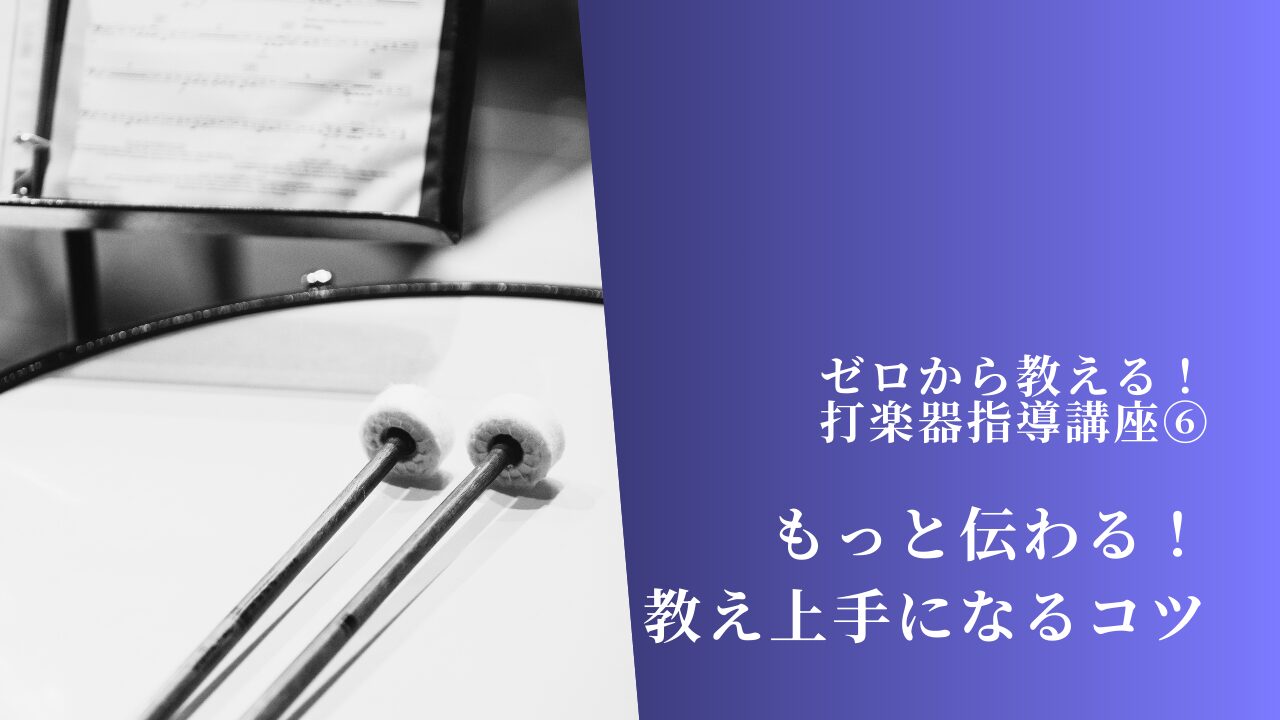






コメント