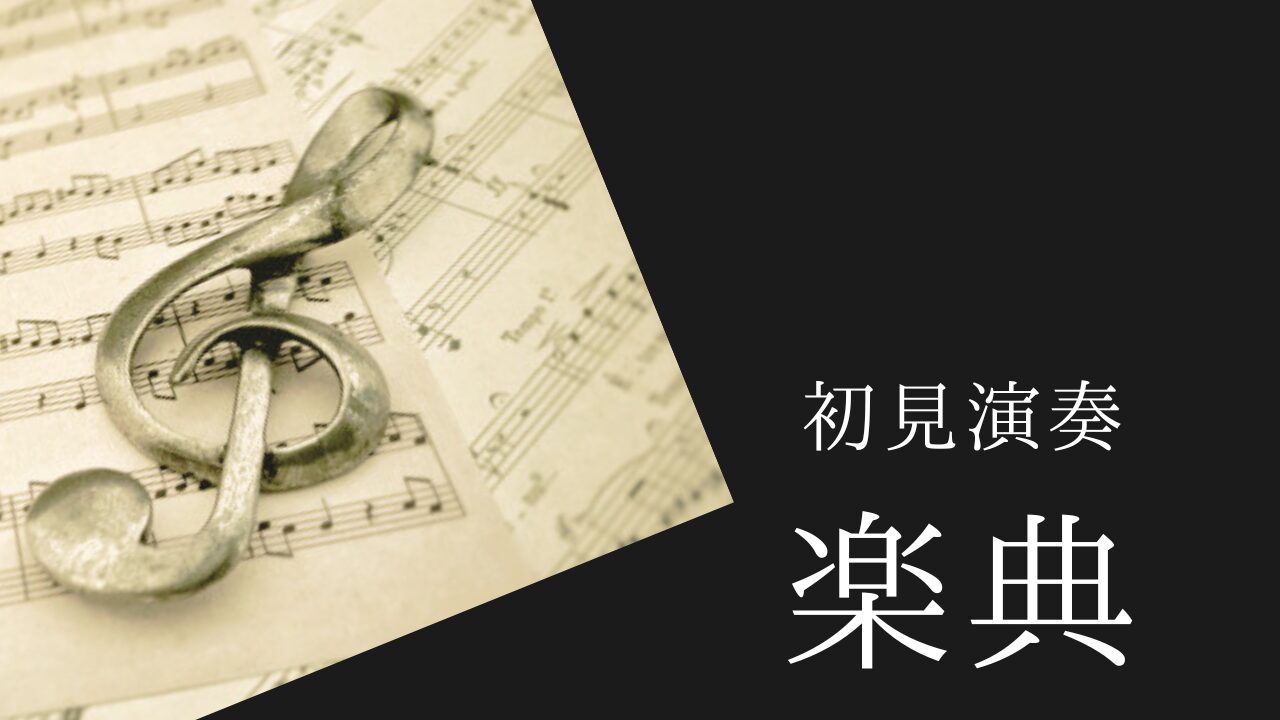こんにちは!
今回は、「初見演奏」について打楽器奏者の皆さんに向けた、譜読みを速くするトレーニング方法と本番で慌てないためのコツを解説していきます!
先生から「はい、この楽譜、初見でやってみよう!」と渡された瞬間、「うわ、できるかな…」と心臓がドキッとした経験、ありませんか?
初見演奏は才能やセンスだけで決まるものではありません。
自転車に乗ったり、泳いだりするのと同じように、正しいやり方を学び、繰り返し練習することで誰でも身につけられる「スキル(技術)」です!
大切なのは、楽譜の情報を素早く正確に処理するための「コツ」を知り、それを体に染み込ませるための「慣れ」を積み重ねることです!
この記事では、次の内容を知ることができます!
- 演奏前に数秒でチェックすべき3つの重要ポイント
- 初見演奏力を高めるための具体的な3つのトレーニング法
- もしミスをしても、演奏を止めずに続けるためのメンタルの鍛え
この記事を読んで、初見演奏への苦手意識を克服し、どんな楽譜にも自信を持ってチャレンジできる「譜読み力」を身につけましょう!
参考にしている教則本はこちら!
演奏前に数秒でチェックすべき3つのポイント
指揮者が「じゃあ、この曲やります」と言ってから、演奏が始まるまでのわずかな時間。
この数秒から数十秒をどう使うかで、初見演奏の成否は大きく変わってきます。
ここでは、演奏前に必ずチェックしておきたい3つの最重要ポイントを見ていきましょう。
- ポイント1:拍子記号と速度記号
- ポイント2:調号と臨時記号
- ポイント3:繰り返し記号や難しいリズム
順番に紹介します!
ポイント1:拍子記号と速度記号
まず最初に確認すべきは、その曲の「骨格」となる拍子記号と速度記号です!
- 拍子記号(4/4, 3/4, 6/8など)
→この曲が何拍子なのか、1小節をどうカウントすれば良いのかを瞬時に把握します。これを間違えると、全てが崩れてしまいます。
- 速度記号(Moderato, Allegro, ♩=120など)
→曲のおおよそのテンポ(速さ)を掴みます。「♩=120」のように具体的な数字が書かれていれば、頭の中でそのテンポをイメージし、速さに備えましょう。
参考

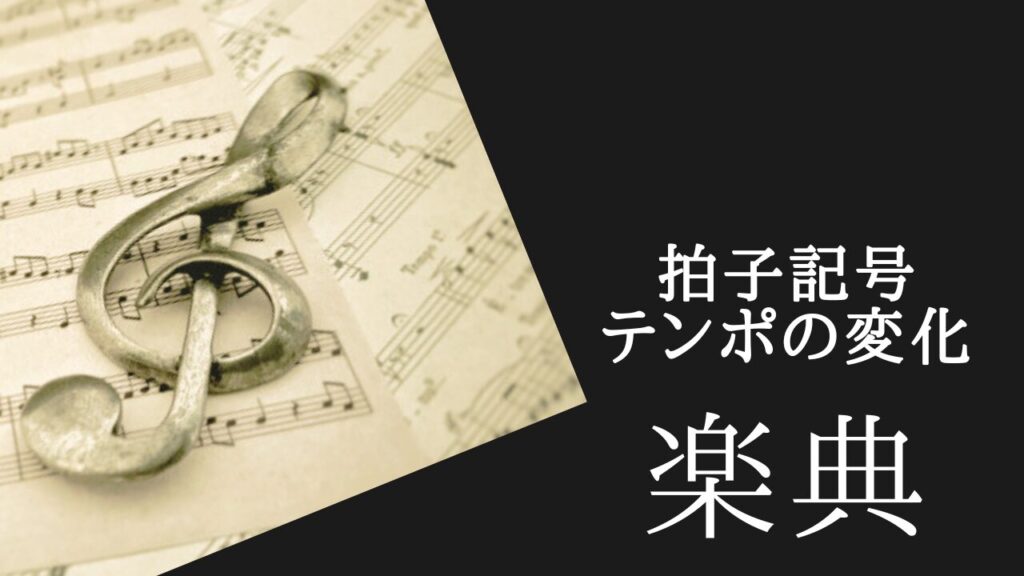
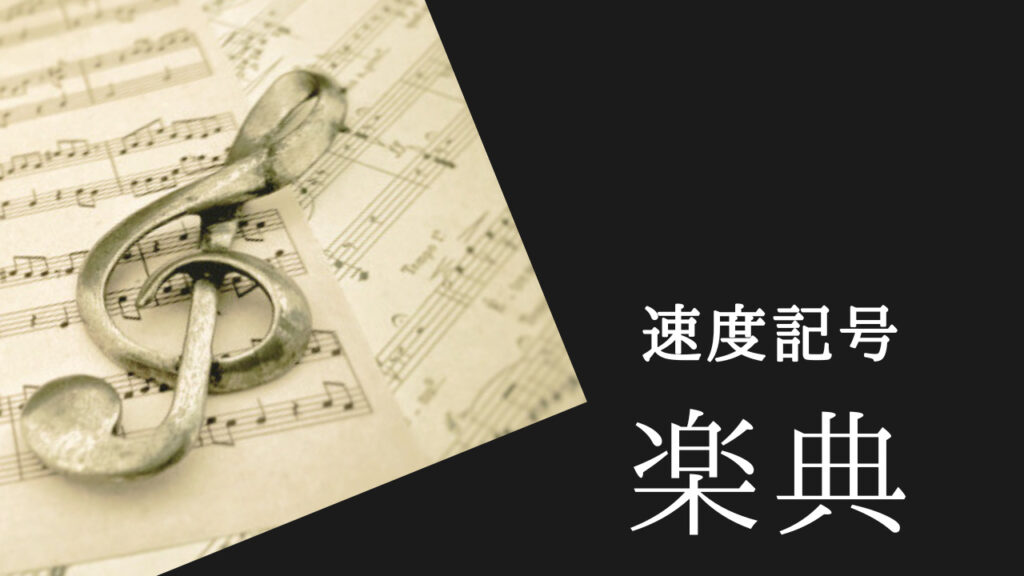
これらを最初に確認することで、曲全体の基本的なリズムとテンポ感を頭の中にセットすることができます。
これが全ての土台です!
ポイント2:調号と臨時記号
次に、音程に関わる調号と臨時記号をチェックします。
これは特に、ティンパニや鍵盤打楽器の奏者にとって非常に重要です。
- 調号(楽譜の左端にある♯や♭)
→この曲で基本的に変化する音は何かを確認します。例えば、調号に♭が3つ(シ、ミ、ラ)あれば、楽譜上の「シ」「ミ」「ラ」は全てフラットで演奏することを意識します。
- 臨時記号(曲の途中で出てくる♯, ♭, ♮など)
→楽譜全体をざっと見渡し、特に臨時記号が多く出てくる箇所や、自分のパートで重要な臨時記号がないかを確認します。これにより、予期せぬ音の変化に慌てず対応できます。
参考
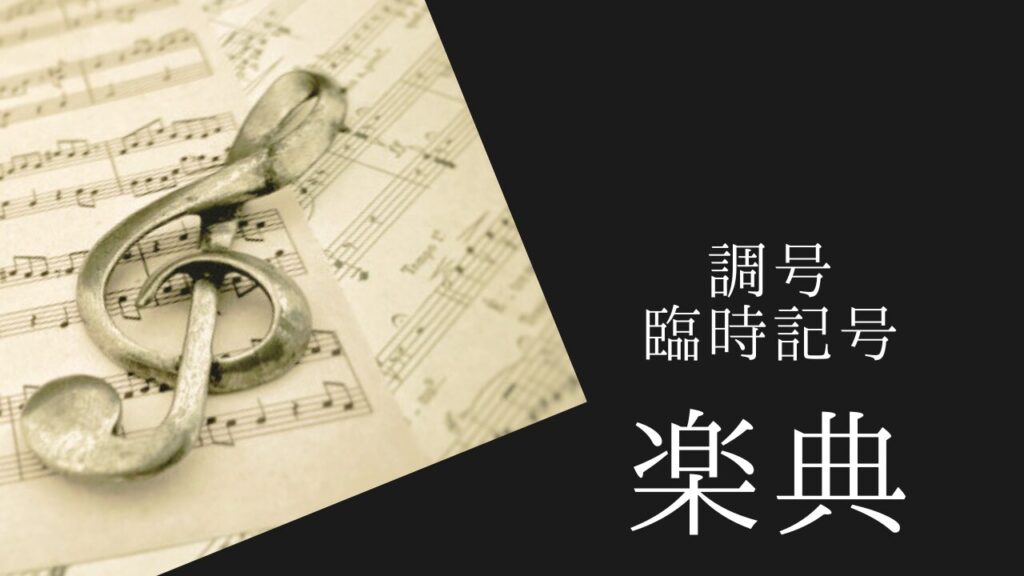
ポイント3:繰り返し記号や難しいリズム
最後に、楽譜全体の「流れ」と「難所」を把握します!
- 繰り返し記号(リピートマーク, D.C., D.S., Codaなど)
→曲がどこからどこへ進むのか、全体の構成をざっくりと把握します。「このリピートマークはどこに戻るんだっけ?」と演奏中に迷わないように、事前に確認しておきましょう。
- 難しいリズムや連符
→自分のパートで、特にリズムが複雑そうな箇所や、見慣れない連符(5連符など)、速いパッセージなどを目で追っておきます。
- セッティングの確認
→複数の楽器を使用する場合は、どのタイミングで持ち替えが必要か、楽器の配置は問題ないかを瞬時にシミュレーションします。
参考

これらの「難所」を事前に認識しておくだけで、心の準備ができ、演奏中に落ち着いて対処しやすくなります!
これを意識すれば、きっと初見でのミスを減らすことができますよ!
【実践】初見演奏力を高めるトレーニング法
次はいよいよ初見演奏力そのものを高めるための具体的なトレーニング方法です。
日々の練習に少しずつ取り入れることで、譜読みのスピードと正確性は格段に向上しますよ!
- トレーニング1:リズム叩き(ソルフェージュ)
- トレーニング2:簡単な楽譜を毎日少しずつ初見で演奏する
- トレーニング3:頭の中で音を鳴らす「内聴」の訓練
順番に紹介します!
トレーニング1:リズム叩き(ソルフェージュ)
これは、楽器を使わずに、楽譜に書かれたリズムを手で叩いたり、声に出して歌ったりする練習です。
リズム感と読譜力を同時に鍛えることができます。
- 手で叩く
→メトロノームに合わせて、楽譜のリズムを手や膝の上で叩きます。音の長さを正確に表現するように意識しましょう。
- 声に出す
→「タン」や「タ」などのシラブル(音節)を使って、リズムを声に出して歌います。これにより、リズムのパターンを体で覚えることができます。
- 休符も大切に
→音符だけでなく、休符の長さも正確に感じるように意識します。休符の部分は「ウン」と小さな声で言うのも良いでしょう。
このトレーニングは、場所を選ばずにいつでもできるのが大きなメリットです。
毎日5分でも続けることで、楽譜を見た瞬間にリズムが頭に浮かぶようになります!
トレーニング2:簡単な楽譜を毎日少しずつ初見で演奏する
初見演奏に慣れるためには、やはり実際に初見で演奏する経験を積み重ねることが一番です。
ただし、いきなり難しい曲に挑戦する必要はありません。
- 自分のレベルより少し簡単な楽譜を選ぶ
→打楽器用のエチュード(練習曲)や、初級者向けの教則本など、無理なく演奏できるレベルの楽譜を用意しましょう。
- 毎日1~2曲、新しい楽譜に挑戦する
→大切なのは、毎日続けることです。たとえ短い曲でも、毎日新しい楽譜に触れることで、脳が初見の情報処理に慣れていきます。
- 完璧を目指さない
→初見演奏なので、ミスをしても気にしないことが大切です。目的は、止まらずに最後まで演奏しきること。間違えた箇所は、後で確認すればOKです。
この「毎日初見チャレンジ」を習慣にすることで、初見演奏に対する精神的な抵抗感が少しずつなくなります!
トレーニング3:頭の中で音を鳴らす「内聴」の訓練
「内聴(ないちょう)」とは、実際に音を出さずに、頭の中で音楽をイメージすることです。
この能力が高いと、楽譜を見ただけで、その音楽がどんな風に聴こえるかを想像できるようになります。
- 楽譜を黙って読む
→楽器を持たず、静かな場所で楽譜を目で追いながら、そのメロディーやリズム、ハーモニーを頭の中で再生してみましょう。
- 音源と楽譜を照らし合わせる
→知らない曲の楽譜を見ながら音源を聴き、楽譜上の音符と実際に聴こえる音を結びつける練習をします。これを繰り返すことで、「この音符の並びは、こんな風に聴こえるんだな」という経験値が蓄積されます。
- 自分のパートだけでなく、他のパートの楽譜も見てみる
→スコア(総譜)を読む習慣をつけると、音楽全体の流れや構造を理解する力がつき、内聴能力も向上します。
このトレーニングは効果が出るまでに時間がかかるため、少し地道ですが、譜読みのスピードと音楽の理解度を飛躍的に高める効果があります!
ミスをしても止まらない!演奏を続けるメンタルの鍛え方
どれだけトレーニングを積んでも、初見演奏でミスをしてしまうことはあります。
大切なのは、ミスをした後にどうするかです。
ここでは、演奏を止めずに最後まで弾ききるためのメンタルについてお話しします。
- ミスは「当たり前」と心得る
- 意識を「過去」から「未来」へ切り替える
- アンサンブルの一員としての責任
順番に紹介します!
ミスは「当たり前」と心得る
まず、初見演奏において、ミスは起こって当たり前のものだと考えましょう。
完璧に演奏しようと気負いすぎると、かえって体が硬くなり、普段ならしないようなミスを誘発してしまいます。
プロの演奏家でさえ、初見演奏ではミスをすることがあります。
大切なのは、ミスをしないことではなく、ミスをした後にどう対応するかです!
「ミスしても大丈夫!」という、ある種の「良い意味での開き直り」を持つことが、リラックスした演奏に繋がります!
意識を「過去」から「未来」へ切り替える
演奏中にミスをしてしまうと、「あ、間違えちゃった…」と、その失敗に意識が囚われてしまいがちです。
しかし、過去のミスを悔やんでいる間に、音楽はどんどん先に進んでいってしまいます。
その結果、さらに大きなミスに繋がってしまうのです。
ミスをしたら、その瞬間に「はい、次!」と、意識をすぐにこれから演奏する楽譜へと切り替える訓練をしましょう。
これは、非常に強い集中力と精神的な強さが求められますが、練習で意識し続けることで、必ずできるようになります。
ミスを引きずらないメンタルこそ、初見演奏を乗り切る最大の武器です!
アンサンブルの一員としての責任
吹奏楽は、たくさんの仲間と一緒に音楽を作り上げるチームプレイです。
もし、あなたがミスをしたからといって演奏を止めてしまったら、周りで演奏している仲間たちも混乱させてしまいます。
アンサンブルの一員として、たとえ自分がミスをしても、全体の流れを止めずに演奏を続けることは、非常に重要な責任です。
「自分のため」だけでなく、「仲間と音楽全体のため」に、演奏を止めず最後まで演奏しきりましょう!
その意識を持つことで、個人的な失敗を乗り越える強い力が湧いてくるはずです!
あなたのその責任感が、バンド全体の演奏を支えることに繋がります!
まとめ
いかがでしたか!
今回の記事では、次の内容を紹介しました!
- 初見演奏の前に数秒でチェックすべき3つのポイント(拍子・速度、調号・臨時記号、繰り返し・難所)。
- 初見演奏力を高めるための3つの具体的なトレーニング法(リズム叩き、毎日の初見練習、内聴)。
- もしミスをしても、演奏を止めずに最後まで弾ききるためのメンタルの鍛え方。
初見演奏は、日々のトレーニングで必ず上達するスキルです。
そして、初見演奏が得意になると、新しい曲に出会うワクワク感が何倍にもなり、音楽の楽しみがさらに広がります。
今日紹介した内容を参考に、どんな楽譜も怖くない、譜読み力」を身につけていってください!